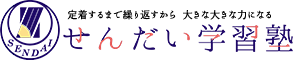成績UPの鉄則
先取り学習の弊害
周りのお子さんが小学生なのに中学生の勉強をしていたり、
ずっと先の学年の内容を学んでいる話を聞くと焦りますよね?
先取り学習は、正しく取り組めればとても効果的ではあるのですが、
残念ながら多くの場合が、正しい形での先取りではなく、
「ただ先に進んでいるだけ」の勉強になってしまっています。
そんな先取りになってしまうと、実は学習として効果が薄いどころか、
むしろ子供の成長にマイナスになってしまうことがたくさんあります。
今回は『先取り学習の弊害』についてお伝えしていきます。
1. 基礎理解の欠如
先取り学習は、表面的な知識の習得に焦点を当てることが多く、
子供が本質的な理解を深める機会を奪うことがあります。
学年が上がれば上がるほど、本質的な理解までに時間がかかりますが、
多くの先取り学習は答えを出すことを優先しています。
計算の答えだけを覚えてしまうと、なぜその計算が成り立つのかを理解する機会が失われます。
将来的に応用問題に直面した際、基礎ができていないために解けなくなる可能性があります。
2. 学習意欲の低下
理解が不十分なまま進むと、学習内容が次第に難しく感じられ、
学ぶこと自体に対する興味や自信が低下する可能性があります。
「答えは当たっているけど中身は分からない」という状況は、
結果として将来的に授業についていけなくなり、
学習へのモチベーションが低下することで、結果的に成績が下がるリスクを持っています。
3. 批判的思考力の欠如
深い理解を伴わない学習は、問題を自分で考え、解決する能力を育む機会を減少させます。
これにより、批判的思考力や問題解決能力が十分に養われません。
定型的な問題に対しては答えられるが、少しでも応用が必要な問題に対しては対応できない、という状況に陥ります。
4. ストレスとプレッシャー
答えを覚えることに焦点が当たると、間違いを恐れて学習がストレスフルになることがあります。
これが長期的な学習習慣に悪影響を及ぼす可能性があります。
テストで高得点を取るために答えを覚えることが重視されると、
試験に対する過剰なプレッシャーを感じ、学習に対するポジティブな態度が損なわれることがあります。
5. 学習の楽しさを損なう
一番大切な、学びの過程で得られる「わかった!」という達成感や楽しさが失われ、
学習が単なる作業になってしまいます。
授業や家庭学習で新しいことを発見する喜びがなくなると、
子供は学びそのものに対する興味を失ってしまうことがあります。
当塾でも先取り学習をさせる場合がありますが、それは深い理解が身についていることが確認できた場合のみです。
例えば、小学5年生が6年生の先取りをする場合は、
小5標準レべル問題 ⇒ 小5発展・応用レベル問題
と更にハイレベルな問題にも取り組んでもらい、それをクリアした子だけが小6の先取りに進むことができます。
きちんとした深い思考が、その子の学力を根本から伸ばします。
「本当はよくわかっていないけど、表面的な理解しかしていないけど正解する」は、本当にその子の可能性を潰してしまう危険な学習です。
ぜひ、定期的にお子様の学習が今どうなっているのかを見直していきましょう!